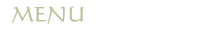NEW ENTRY
(07/14)
(07/12)
(07/02)
(06/28)
(06/27)
[PR]
裏界線:589ss
タテタカコのアルバムを久しぶりに聞いてます。
このひりひりした感覚がたまらない。
ひまわり 《スコール》
あの頃ひまわりが怖かった、どうしてだろう。たぶん自分よりもずっと背が高かったからだろう。大人の女の高さから見下ろしてくるひまわりに囲まれていると、息苦しくておそろしくて、その場にうずくまってしまいたくなっていた。
どこまでもひまわりの群れが続いている。ちいさな家を囲んだひまわりの森。恐ろしくて、腹立たしくて、自分よりもちいさいひまわりを選んで、けとばした。折れてしまって急に怖くなった。転がるように走って逃げた、臆病者の子ども。あのころの自分。
「ひまわりは、嫌い?」
「……嫌いだ」
「めずらしいな、おまえがちゃんと《嫌い》って言うのって。《好きじゃない》じゃ、ないんだ」
あんたの影が俺の顔にかかる。寝転がる俺からは、太陽をさえぎる笑顔が影に見える。目をそらすように寝返りを打って横を向く。ちくちくと顔をつつく草の感覚。立ち上る土の匂い。
「ひまわりは嫌いなんだ」
不思議そうに首をかしげるしぐさ。見えなくても手に取るように分かる表情。
くっきりとした眼。太陽の光が差すと金色にも見える。青空の色のマント。色石の飾り。
「強そうに見えて、そうじゃない」
「へえ…… どういうことなんだ?」
「強いふりしてるように見えるから、苦手なんだ」
俺があの日折ったひまわりは、そのまましおれて枯れてしまった。
みんな知らない。ひまわりは本当は強くない。俺は誰かを傷つけられる。子どもの頃だってそうだった、何も考えない無方向な怒りでも、誰かを傷つけるには十分だ。
あんたは少しひまわりに似ていると思う。そう思ってあんたを見ると、俺は急に怖くなる。あの日みたいな無意味な苛立ちが、いつかあんたを壊さないだろうか。子どもじみた怒りでけり倒して、俺はあんたを折ってしまわないだろうか。
俺はまだ、ひまわりが嫌いだ。
心細いときに歌う歌 《ジタン》
オレはさみしいなんて思わない。誰かと自分を比べて、自分のほうが苦しいなんて思わない。そんな弱虫になりたくない。傲慢なひとりよがりになんて、なりたくない。
オレより不幸なひとなんていっぱいいる。家族がいないやつなんて世の中には一杯いる。自分と似たやつが誰もいないやつも、未来が見えなくて怖いやつも、いじけてひとりぼっちでさみしいやつも、人ごみを見渡すと五万と見つかる。
だから、オレがもし泣きたくなっても、それは泣いてもいい理由にはならない。
他の誰かにとっとかなきゃいけない。席の数が決まっている、子どもが泣いてもいい場所なんて。
ときどき記憶が遠い星みたいに明滅する。あるいは波間から見る町の明かりみたくに。遠く近く、今のオレからは見えない記憶がゆらいでいる。たくさんの人で囲むあったかい食卓。誰かの笑い顔。歌声や舞台の喧騒。この手を握り締める、小さいてのひらの感触。
だからオレは怖くなんてないんだ、とそのたびに考える。
大丈夫、今は思い出せなくても、オレにはちゃんと帰る場所がある。さみしくないし苦しくもない。むなしくない。誰かに終わらせてもらいたくなんてない。
大丈夫、大丈夫、オレはぜったいに大丈夫。
何があっても平気。心細いなんて絶対に言わない。
「……止まないな」
「ああ」
ぽつんぽつんと軒から雨がおっこちてくる。顔を出して空をみた拍子に、でっかい水滴が鼻の頭におっこちた。思わずびっくり眼になって振りかえると、隣で雨宿りしてたやつがすごく変な顔をした。おかしい。オレはニッと笑って、大きな瓦礫の影に戻る。変な建物だな。継ぎ目のない建材からぶっとい鉄の棒が突き出して、あちこちで出鱈目な方向にまがってる。
「いつになったら止むんだろ」
「さあな」
「こんな場所で降ったってしかたないのに」
嘆息する。降ってくる雨は地面に吸い込まれないで、そのまま灰色の流れになってあちこちのひびわれに吸い込まれていく。薄暗い空に青い光が映える。砕けてちらばった古いガラスや、ねじりこまれたようになった何かの建物の名残らしきもの。
「せっかくだったら、もうちょっとちゃんとした屋根の下にいるときに降ってもらいたいもんだな。それか虹がきれいそうな場所にさ?」
こわい。どうしよう。こういう場所は苦手だ。そんな風に胸の中で尻尾のあるちっちゃい生き物が震えている。オレはもし出来るものなら、自分の胸を切り開いて、その邪魔者をつかみ出してやりたいと思う。冗談じゃない。怖いわけない。今はスコールも一緒なんだから。護ってやらなきゃいけないんだから、こいつを。
でも、振り返ったとき、急にばさりと頭の上から何かがかぶさってくる。革の匂いと鉄の匂い。眼をまたたいて見上げる。スコールがちょっと哀しそうな顔をしていた。眉の間に皺を寄せて。
「な、んなんだよ? 急に?」
「無理に喋るな」
「……」
「無茶は分かるんだ。だから黙ってろ。……それか、口寂しかったら歌でも歌ってろ」
しばらく声が出なかった。スコールはそっぽを向いた。何か言おうと思った、喉がこわばって出てこなかった。
どうしようかなあ、としばらく思って、どうしようもないなあ、としばらくして気付いた。
なんか手が震えてる。なんでだろ。かっこ悪いな、どうしよう。
思ってるとスコールが、ぽつんと独り言みたいにいう。
「あんたの歌は、好きだ」
ああ。
「……ありがと」
―――自分に嘘をつくのは簡単でも、ひとに嘘つくのは、そうじゃないんだなぁ、って思った。雨はしとしと、まだまだ降り続いていた。
寂しい寂しい ぼくだけ 寂しい
体いっぱい臭わして 暮らしてた
苦しい苦しい ぼくだけ苦しい
世界一の不幸 背負っていた
心細い時にうたう歌
心細い時にうたう歌
《秘密の物語》 (バッツ)
ここにはあなたがいて とりとめのない話をするでしょう
どうしても越えられない海の 大きさについて
なぁジタン。
もう寝てるよな?
おまえが聞いてないから、この話をするよ。
おれの一番の秘密の話。
おれのおふくろが死んだのは、今のクラウドと同じくらいのころだった。
おれはまだ子どもでさ、小さな村で暮らしてて、おふくろがいて、おやじも時々いて、友達がいて、毎日がとても静かで……
おふくろは刺繍がとても上手だったから、ちかくのおばさんたちと一緒に刺繍を作って、それを卸して、ずっとひとりで暮らしていた。おやじは急がしくてあんまり帰ってこなくても、だからあんまり苦にならなかったらしい。ときどきのティナみたいな緑色の髪をしてて、笑うのが好きでにぎやかなのが好きで、明るくて、子どもっぽくて。
それではたちを過ぎたあたりからめまいがするって言って歩けないことが多くなって、ある日いきなりぱたっと倒れて死んじゃった。
おふくろの父さんと母さんもそうだったって。
憶えてないけどその父さんたちや母さんたちも一緒だったって。
家系なのかな、みんなそうだったらしい。緑色の髪をしていて、良く笑ってよく喋って、風と友だちで、あんまり長生きできない。
だからおやじはおれもそうなるんじゃないかって、おれがほんの子どもの頃から、猛烈に怖がってた。
だからかな、何処にでも連れてってくれたし、なんでも教えてくれた。おふくろを連れて行けない程度には危険な旅だって知ってたはずなのに、おれを傍から放すことだけは絶対になかった。怖かったんだと思う。たったひとりの家族が、もしかしたら自分より先に死んじゃうってことが。
おっかけてくる時間から逃げるみたいに、世界中旅した。
最期までずっと一緒だった。
だからおれは、ひとりになるまで、自分が残るなんて思ってもいなかったんだよ。誰かをひとりぼっちにする準備はできてたのに、逆は、そうじゃなかった。ちょっと応用すればいいって気付いたら簡単だったけど。誰かを残してく覚悟はあるのにその逆はできないなんておかしいだろ。だから死ぬのは平気だった。怖いけど、怖いってこと自体が平気だった。
露に濡れた草も、黄色い砂の砂漠も、冷たい風が削る山も、雪原も、全部がおれの寝床だった。
晴れた日も、星の多い日も、そうじゃない日も、青空も夜空も、ぜんぶの空がおれのテントだった。
でも、今になって思うんだ。
そういう風に生きるのって、ひょっとしたら、ものすごく間違ったことなんじゃないかって。
生きてる人間は死神と友達になっちゃいけない。寂しさや恐ろしさと仲良くしちゃいけない。そういうやり方を憶えるのは、いけないことなんじゃないかなって思う。どうしてだか分からないけど。でも、そうやって生きることは、何よりもいけないことで、おやじやおふくろを哀しませることじゃないかなって最近思うんだ。
だからおれも、死ぬことを怖がってみようと思う。
ひとりぼっちを寂しがって、別れを嫌がって、もがいてみようと思う。おれにとっては難しいことだけど、でも、今からあんまり長い時間じゃなくても、そうやって生きてみたいと思う。だって、せっかくおまえたちと会えたんだから。ジタンやスコールや、みんなと。絶対にあえなかったはずの人たちと。
あんまり長生きできないかもしれないのに、死ぬのが怖がりながら、どうやって生きたらいいのかわからないけど。
でもおれ、やってみるよ。
……ごめんな、ジタン。
もしかして、泣いてるのか?
PR
- トラックバックURLはこちら