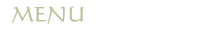NEW ENTRY
(07/14)
(07/12)
(07/02)
(06/28)
(06/27)
[PR]
すてきな三にんぐみ(589・習作)
今日は拍手をたくさんいただけていて、なんだかすごく嬉しかったです。
応援してもらえたと判断してもいいのかな?
今回うpした【ガラス玉遊戯】の新作は文章がものすごく辛かったのですが、それでもなんとか読めるものにしあがっていたのだと思いたいです。救いようの無い悲惨なアレコレですが…
浜辺に漂着するすりガラスって、【シーグラス】とかいろんな呼び名があるみたいですね。私が知ってる名前だと【ドリフトグラス】っていうのが一番印象的でした。サミュエル・R・ディレイニーという人の旧い旧いSF作品ですが、とても印象的なフレーズがあって、以前のジャンルでもエピグラフに使ったりしていました。
ちなみに【Drift】は【さ迷う・漂流する】という意味合いらしいですが、日本語で発音すると、どうしてもドリフターズのことを思い出してしまうw
ところでここから先は習作です。
文章が書けなくなったらまずいんで、ちょっとずつ練習。絵本の”すてきな三にんぐみ”はとてもいい感じでしたね。
スコールの手が好きだ。
鉄臭くて硝煙臭い。傷だらけの火傷だらけで、そのくせまだ指がほっそりとして、バッツの手よりも小さい手。
血の臭いなんてしない。スコールの手に、人間の血や肉みたいな汚いものを触らせるなんて、神様に失礼なことだと思う。
そんなことをまともに話し合ったことはないけれど、バッツだって同じことを考えているのだろうとジタンは知っていた。二人はバディだ。たぶん、出会ったときからずっと。だからお互い、自分たちの何が悪いのかを全部知っている。
やったことを一つづつ知らなくても、何が許されなくて、何が業なのかを知っている。でもスコールのことは知らない。スコールの手は、まだ、誰かの血のこびりついた、あの生暖かい安心を知らない。
二人を踏み台にすれば、一人くらいは外の世界に出してやれるかもしれない。そんなうそ臭い希望が胸を掠めることがある。単なる錯覚だ。それくらい知ってる。でも夢くらい見たっていいじゃないか。
この世の中にはきれいなものとか穢れないものが本当に存在している。そんな、見たことも無い遠い場所のことを考えるのが、二人にとっての夢だった。物語、だった。
「ただいま」
「お帰り!」
「おいこのドア、開かないよ? 荷物ひっかかってないか?」
「……」
無言でのっそりと起き上がったスコールが、手を伸ばしてドアの傍に転がっていた箱をどける。するとバッツが尻でドアを押しながら、部屋の中に入ってきた。両腕にかかえた紙袋には満載に詰め込まれたスパムやスキムミルクの缶詰。どうやら今日の収穫は上々だったらしい。「今日も生野菜なかった」とぼやきながら、バッツは狭い部屋に潜り込んでくる。
頭上の蛍光灯は不安定に点滅していて、しっかりとした明かりがついているのはREDライトを使った手元灯くらいのものだ。レザーのすりきれたソファの上で、でかいネコが尻尾をくねらせて大あくびをする。蜂蜜色の長い尾が軽くソファの背を叩いた。ジタンは目をまたたく。
「おかえり、バッツ。どぉ? なんかいいもんあった?」
返事代わりにタバコが一箱飛んでくる。ぱしりと顔の前で受け取ると、ジタンはにんまりと笑みを浮かべた。チェシャ猫の笑みだ。
「腹減ったろ。今、食うもん作るよ」
「肉食いたい」
「肉ならあるけどさ… 肉しかねえよ」
なんだこれ、と愚痴りながら、重たい鋳鉄のフライパンを引っ張り出してくる。ガスボンベをひねり火をつける。台所に置かれた椅子のうえに座り込み、バッツは鈍いナイフで缶詰と格闘し始めた。ジタンはのんびりと一本のタバコをパッケージから引っ張り出す。
REDライトの下では、スコールが黙って銃の整備を続けていた。クローヴの香りがするタバコは、火をつけるとぱちぱちと音を立ててはじける。煙は安い菓子の匂いがする。ジタンは目を細めて作業台を見下ろす。
鈍い銀色に光るSIG。ちんぴらが使うには上等すぎる高価なジッポーのような細工。スコールが愛用のSIGを整備する動作には、洗練された機械的さが存在している、と思う。パーツを分解し、傷一つなく磨き上げ、油を引き、動作を確かめる。毎日同じ作業を繰り返す。一日も欠かさずにだ。
最期に引鉄を戻し、作業を全部終えたところを見計らって、ジタンはのんびりと声をかけた。
「タバコいる?」
「いや、いい」
目を上げて、ちいさくため息をつく。ちゅん、と熱した鉄に油を落とす音がした。コンロのほうからだった。質の悪い魚油の臭い。「うえ」と鼻の頭にかるく皺を寄せてみせる。スコールは少し困った顔をしたようだった。
「バッツぅ、なんの匂いだよ?」
「肉。スパムだって」
「うえー」
「我慢しろよ。【上】にいったらいいもんたらふく食えるんだしさ!」
はじけるように帰ってくる口調は明るい。だが、その意味は聞いただけでも明らかで、ジタンとスコールは思わず目を見合わせる。ジタンの反応のほうが早かった。ソファを滑り降り、放り出されていた紙袋に手を突っ込む。端末が出てきた。ログをチェックする。新しい【依頼】が、そこに入っていた。
次の仕事は上のプレートだった。次のターゲット。上層部のステーション。爆破し、ターゲットをしとめ、そして、戻ってくる。テロ組織の下請けか、とジタンは冷めた気持ちで思った。くだらない仕事だ。自分で手を汚すのが怖いんだったら、そもそも、こんなことなんて考えなければいいのに。
「バッツ……」
「スコール、そこに地図も入ってるから頭に入れといて。お前の分、特盛りにしてやるからさ。次も頼ることになっちまいそうだから」
「……」
口を開けて何かを言いかけて、途中で黙って、手元に目を落とす。一部始終を見届けてからそっと目をそらす。ジタンは明るい声で呼びかける。
「なぁバッツ、上のプレートで飯食う時間とかもあるわけ?」
「あるある。美味いエビでも食おうぜ。心当たりがあるからさ」
「へぇ!」
「特にスコール。ちゃんと食わないと背が伸びないぞ~」
じゅうじゅうと音が聞こえる。さっきまでの吐き気がしそうなガソリンめいた臭いが、ガーリックやジンジャーで丁寧に調整されて、なんとか人間の食べ物らしい香りへと色づけされていく。誰かの作る、上のプレートの連中が食う飯よりさ、とジタンは思った。
バッツの作る飯のほうがずっと美味い。ちゃんとした食材とキッチンと、それから安全な食卓と、三人分の椅子と。それがそろっている方がきっとずっと美味しくて楽しい。一呼吸だけ考えてすぐに打ち消した。子どもじみた夢。
スコールは今度は、作業台の横に寄せてあったカートンを手にとっていた。9mmパラベラムの先端から鋼をはがし始める。そうやって加工した弾を通常の弾と混ぜ合わせるのがスコールの流儀だった。中の鉛をむき出しにした弾は、貫通力は落ちる代わりに破壊力が増す。
「なぁ、スコール」
ジタンは、ことんと作業台に顎を乗せた。上目遣いにスコールの顔を覗き込む。ふと、困った顔をする。瑠璃色の目。
「なんだ?」
「お前さ、上に言ったら何が食べたい?」
「何がって……」
「チョコレートとかさ、ケーキとか。アイスでもいいよな。なんでも買ってやるよ?」
可愛い坊やのために、とジタンはからかう声を出す。スコールは顔をしかめた。
「なんで、俺だけ子ども扱いになる?」
「食べないと背が伸びないんだろ」
「……」
「可愛い子には甘いお菓子を!」
ジタンは口ずさみ、けらけらと笑う。手を伸ばしてスコールの指を掴んでやった。火傷だらけの器用な手。
「やめやめ、そんな辛気臭いの後にしよ。バッツぅ、飯まだー?」
「もうすぐ!」
キッチンから、歌うような声。
そのままことんと顎を乗せて、スコールが手を動かせないようにしてやる。ニッと笑ってみせると、スコールはとうとうため息をついた。そのまま手を伸ばしてジタンの耳の後ろをかるくくすぐる。指先が心地よい。ごろごろと喉が鳴る。
鉄臭い、硝煙臭い手。傷だらけで火傷だらけ。なのにどこかまだ華奢で端正で。
人を殺す話をしたとき、ふと哀しそうな色が目をよぎる。隠すために目を伏せる。そんなスコールが、とても大切だ、とジタンは思う。
鼻歌がキッチンから聞こえる。ブリキの錆がはいった缶詰から、バッツが美味い晩飯を作る。明日も人を殺す日だ。
美味いものを食わせてやりたいな、とジタンは思った。バッツとスコールに。明日が待ち遠しい。それ以外は何も思わないし、思いつかなかった。
今までだって一度も。
【ここまで】
荒事請負屋な589でした
PR
- トラックバックURLはこちら