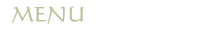NEW ENTRY
[PR]
感想じゃないけど
慶ちゃん、あんたバカだよ。
そんなことで一々傷ついてたら、生きてくことが辛くなるだけなんだよ。
アニバサ11話みて、なんかたまんなくなって、書きました。
あとで後悔して消すかもしれませんし、ちゃんと最後まで書いてうpするかもしれない。
あと小太郎がマジで人間なのかどうかと、オクラの日輪版サテライトシステム(byガンダムX)にいろいろ悩みました。日輪は出ているか?
追記:
慶ちゃんがあそこまでして剣を抜くことを拒むのは、
「愛する人に刃を向けられる悲しみ」を、どうしても秀吉に味あわせたくないからなのかなって思いました。
それが痛みなのかは人によって違うだろうし、そういう考え方を他人に強いる傲慢は否定できない。
でも、自分が味わった中でもっとも辛かったものを、愛する人には味わってほしくない、というのは、
感覚として確かに理解できるものだと思うんだ。
誰からも理解されなくても、まったく無力でも、己の意志を貫く。
これを愚鈍といい、愚直といい、そして、正義というのかもしれません。
*一部、四肢欠損などの痛い表現を含みます
これは遠い昔ではなく、今と同じ時代のお話。
ここではないどこかの、ありふれたお話。
初秋。
地平線まで続く草原が、白い穂をゆらし、あわい金色の色をまとう季節。
ジープは舗装の悪い道にがたがたと揺れながら草原を行く。左右には草の海がどこまでも広がり、遠い山陰は地平線の彼方に藤色に霞んでいた。こうやって草原を行き始めてすでに丸一日。太陽はもう西の空へとゆきかかり、どこまでも青かった空の色が、乳を混ぜたかのようにゆるみつつある。
「―――大したものですね、ここまで誰もいないとなると」
ジープの乗員は三人。徽章をつけた上級軍人が一人と、その随行者がふたり。
上級軍人、そして、随行の兵のひとりはこの地方の生まれだ。だが、最後の一人はここから離れた山間の生まれ。こういった景色を珍しがってしきりにいろいろと言っていたのは最初の半日くらいで、今では何もない景色にすっかりうんざりしているらしい。ハンドルを握りながらの言葉も呆れ気味だ。
「これだけ平地があるのに、開墾もせず、牧畜もせず……」
「……しないのではない、出来ないのだ」
「秀吉様?」
後ろの席の男が、重い口を開く。巨漢、といってもいいだろう。刻んだように厳しい面差しをした、日に焼けた男だった。金色に沈み行く平原を見回す目は、赤い琥珀に似た色をしている。
「このあたりの土地は開墾に向かぬ。地味が薄く、草を刈ったところで満足な麦も作れん。玉蜀黍をすこしばかり撒くのがせいぜいといったところだ」
「成る程…… だが、せめて山羊とかを飼ったりとかはできぬのですかのう」
「居るはずだ、見ないだけだろう」
男は、短く、言葉を切る。
「この草原には地雷や不発弾が多い。恐れて牧童が出歩かぬから、あまり目にせぬというだけだろう」
―――そう、友が言っていたのを、聞いた記憶がある。
そう思い出し、男は、秀吉は、口をつぐんだ。ただならぬ気配を察したのだろう。随行者たちもお互いに目配せをしあい、それきり、黙り込んだ。
そこは、草原と山に囲まれた場所。
いくつもの国々が、お互いの民族の誇りをかけあって、終わることのない戦争を続けている国だった。
大国と大国が戦争をしたのがもう何十年も前。それから後、この場所では終わることなく小さな戦が続いていた。お互いに民族の血を争い、あるいは政治的信念を争いあい、ときにはただ、明日生きていくための糧を奪い合うために、終わることなく戦い続けてきた。
ならば、この草原の国に生まれたということは、将来は兵士となって戦うために生を受けたのと同義だ。男達は皆年頃になると徴兵され、兵隊となる。歩いて超えることができる距離にある国境をかけて争う。死ぬまで。
あまりに虚しい、哀しい生き様だ。
そんなもののために生まれてきたなんて、思いたくない。……別の生き方をしたい。もっと、何か、別の。
秀吉とその友が道を別ったのも、それが、原因だった。
夕刻ごろ、草原に太陽が沈むと、遠くにかすかな光が見え始める。
そこが、彼らの目的地だった。
*******************
ただどこまでも続く草原の中に浮かぶ、古い古い石組みで作られた浮島。
それが遠くからその村をみた印象で、実際のところとしてもそうそう間違っているわけではない。もう千年も昔に作られた石垣をそのまま使った小さな村は、小さな屋根を寄せ合い、庭の間で山羊を飼い、炊事のための煙をかすかに立ち昇らせていた。リンゴの木が見える。ぶどうの木も、小さな畑も見える。
軍属とすぐ分かるジープを見た村人たちは、一目でその場に凍りついた。随行者のひとりが助手席を降り話をする。目を丸くした娘が、近づいてきた子どもたちに話をする。あちら、こちらで小さな窓が開けられる。住人たちがこちらの様子を伺う。
「気に入りませぬ」
「仕方があるまい」
むっとした風に呟く随行者に、秀吉は短く答える。
家々の間から投げかけられる、困惑したような、怯えたような目、目。
「この土地には、我らのようなまともな軍人など、訪れるような理由もないのだ」
細い道を、体を斜めにするようにして通っていく。最初に感じた違和感は刹那、心はすぐに10年も昔に戻っていく。石壁のあいだの入り組んだ小道。こんなにちいさくて、箱庭じみていただろうか?
『ひでよし、こっち、こっち!』
幼馴染の声が、まるで幻聴のように、まぶたのうらに思い出された刹那。
「……秀吉どの?」
懐かしいりんごが花を咲かせた小さな家が、小道の向こうに現れる。
出迎えてくれたのは友人の叔母だった。かつてはほんの少女だったものが、今では穏やかな風貌のうつくしい女になっている。秀吉と随行者のために路地に卓をだし、なつかしい匂いのする茶をふるまってくれた。
「まさか、こんな急にたずねてきてくれるなど、思ってもおりませんでした」
「尋ねる、と手紙を送らせたはずだが」
「このあたりじゃあ、手紙なんてまともに届く方が稀です。10通送れば、そう、1通くらいは届くこともありますけれども」
ふちの欠けたティーカップには見覚えがあった。誰にも気付かれぬよう、指先でそっとなぞる。残りの二人はようやっとたどり着いた揺れない椅子にほっとしているらしい。焼きたてのブリヌイにはたっぷりとジャムとサワークリームを添え、干したクランベリーの茶の酸っぱさを喜ぶ。二人の様子を見ているまつはうれしそうだった。昔からこういうひとだった、と秀吉は思い出す。
「利家殿は」
「犬千代さまなら出稼ぎに。半月ほどにもなりましょうか、ここから何日も言ったところで、そろそろ麦を取り入れる時期がきているのです」
ここじゃあ、大の大人が暮らしていくような仕事もありませんものね。そう言って、まつは、少しだけさみしそうに微笑んだ。
「……」
一番聞きたいことが、まだ、聞けない。
秀吉は黙ったまま、カップを口に運ぶ。
あれはいるのか。
何をしているのか。
「それにしても、こんな田舎まで、よくも尋ねてきてくださいましたこと!」
まつは唐突に、明るい声でわらいだす。
「あなたがた、道が悪くてお尻が痛くなったでしょう。犬千代さまのベットもあいておりますし、ここの村には旅籠もないわ。今日はうちにお泊まりなさい。おなかも空いているんでしょう?」
「いいのか!?」 と、顔を輝かせて飛びつくのが一人。
「おい遠慮しろ貴様!」と、しかめっつらで脇に肘をくれるのが一人。
「いいのよ、あまり静かだと気がめいりますもの。あれのお友だちだったら、誰であっても大歓迎。そうね、すぐに夕飯の準備をしなくては。さっそくガチョウを絞めなくてはね。慶次も呼んで来ないと」
秀吉は、自分のカップの中に、ちいさく波がたったのを見る。
まつは立ち上がる。「我も」と秀吉も続く。二人がそれぞれに意外そうな顔をする。自分らしくないと、自覚はしていた。
まつは勝手知った様子で木戸をくぐった。鍵すらかけなかった。秀吉も後に続いた。昔から知っている懐かしい路地。踏み出す足が、記憶の中の足取りに重なる。一歩歩くごとに、時間が撒き戻される。心が昔に戻る。
時間が昔に戻ったみたいだ。
ここは、あの頃の村じゃないか。
目の前に石垣で囲まれた小さな果樹園が見える。リンゴが青い実を揺らしている。ああ、あの枝ぶりはおぼえている。あれは、あそこの木の下で寝るのが好きだった。じゃあ、あれは、またいつものようにだらだらと惰眠をむさぼっているのか。あの木の下で。白い花の咲く場所で。
「慶次、慶次!」
まつが呼びかける。すこし間があいて、何か、音がした。かしゃり、という金属音。かつん、という木の音。
かしゃり、かつん。かしゃり、かつん。
かしゃり―――
「ん、どうしたんだよ、まつねえちゃ……」
内側から木戸を押して、ひとりの、大柄な青年が顔を出す。
秀吉は思わず、息をすることを忘れる。
栗色の髪を、頭の高いところで結わえていた。日に焼けた肌。ひとなつこい茶色の目。肩が広くて大柄な。頑丈な手足をした。
その手足がない。
空の右袖が結ばれていた。足は、なかった。ズボンの片方は空のままだった。もう片足には古びた金属の装具がつけられていた。四肢の中で唯一残った方の腕には、松葉杖を手挟んで。
「秀吉?」
びっくりしたように丸い目をして、こちらを見上げる。
その目も、片方しか、ない。
「……慶次」
声が出なかった。話を聞いて、予想はしていたはずだった。なのに何もいえない。言葉が出てこない。
向こうも同じだった。目を見開いて、何か言いかけて、言葉を選べずにいる。何度か口を開きかけてはまた閉じた。かしゃ、と音がして。
「……うわぁ!?」
「っ!」
無意識に前に出ようとした瞬間、体が、前にのめった。
秀吉はとっさに腕を伸ばす。慶次を抱きとめる。その瞬間、鳥肌が立った。軽い。あまりに軽すぎる体。
「慶次! 無理はやめなさいと、言っているのに!」
「たはは…… ごめん、ごめん。びっくりしちゃってさあ。まさか、会いに来てくれるなんて、思ってもなかったから」
あわてた口調のまつに叱られ、へへ、と慶次はくすぐったそうに笑う。抱きとめた腕の、濃緑の軍服に、頬を摺り寄せる。髪からはりんごの花の匂いがした。昔と何もかわらない匂い。笑顔。
「秀吉、秀吉」
片方だけの腕で、抱きついてくる。その力は記憶の中にあるものと比べたら、哀しいほどに頼りない。
「ほんものの、秀吉だぁ……」
かみ締めるように呟いて、顔を上げて、笑う。
秀吉は、何もいえなくなる。
- トラックバックURLはこちら